「情報格差の例って、どんなものがあるのだろう?」
「情報格差に対して、高齢者はどう対応していけばよいか」
これらのようなことを考えている方たちに、おすすめの記事となっています。
僕は、情報の恩恵を、多大に受けています。
最近は、月に10冊くらい読んでいるんじゃないか、と思うほど、情報収集に熱が入っております。
そんな僕ですが、身近にいる高齢者の方たちを見て、思うところがありまして……。
それは、情報をうまく使えていない、ということです。
「あ、今こういう対処をすれば、こんなにいいことがあるのに……」とか、色々思うことがあります。
そのような情報を受け取るメリットと情報を受け取れないデメリットを知っているので、今回の記事を書けるかな、と思いました。
今回の記事を読むことによって、情報格差のことについて、なんとなく理解を深め、身近に高齢者がいる場合などは、改善するヒントを少々得られるかな、と思います。
僕は、専門家というわけではありませんが、多少の客観性を確認しつつ、自分の意見を書いていきますね。
よかったら、参考にしてみてください。
それでは、始めていきましょう。
情報格差の身近な3つの例

情報格差の例として、以下の3つを挙げておきます。
- 高齢者のテクノロジーに対する不慣れ
- 情報を獲得するツールを獲得できない
- 教育の程度による差異
順番に、解説していきますね。
その1:高齢者のテクノロジーに対する不慣れ
情報格差の例その1は、高齢者のテクノロジーに対する不慣れです。
高齢者にとって、テクノロジーは、生まれた時代にはあまりなかったもの、と思われます。
最近になって、スマホやAIなどが、出てきていますよね。
このような背景により、テクノロジーに対して、不慣れな部分が出てきている側面もある、と思います。
例を挙げてみましょう。
- スマホを活用できない
- 電車に乗りづらい
- 通販を使いづらい
このように、高齢者がテクノロジーを上手に使えないことによって、生活に支障が出てきている部分もある、と考えます。
テクノロジーの不慣れによって、情報格差が出てきているかもしれませんね。
その2:情報を獲得するツールを獲得できない
情報格差の例その2は、情報を獲得するツールを獲得できない、ということです。
ここでは、身近な例として、「検索」を挙げてみましょう。
検索をすると、ありとあらゆる情報にアクセスでき、行動を起こすことができます。
しかし、検索ができない、となると、無限にある選択肢を使えない、となってしまいます。
もちろん、検索できなくても、日常生活を送ることはできるかもしれません。
しかし、有益な情報を得て、質の高い行動を起こすことができなくなるので、情報格差が生じると言えるかな、と思います。
その3:教育の程度による差異
情報格差の例その3は、教育の程度による差異です。
これは、様々な例があると思いますが、本質的なことを言うと、主に以下の3つになるかと思います。
- 教えてくれる人の質
- 教えてくれる人との出会い
- コミュニティなど
教えてくれる人の質が低いと、有益な情報は、入ってきづらくなりますよね。
そして、教えてくれる人と、適切に出会わなければ、やはり情報は、入ってきづらくなります。
最後に、コミュニティですが、適切なコミュニティに所属していれば、適切な教育を自然と受けられるかもしれませんね。
つまり、この中で、適切なコミュニティに入れば、適切な出会いが生まれ、適切な教育を受けられるかもしれませんね(1つの方法として)。
情報格差が起こる原因とは?
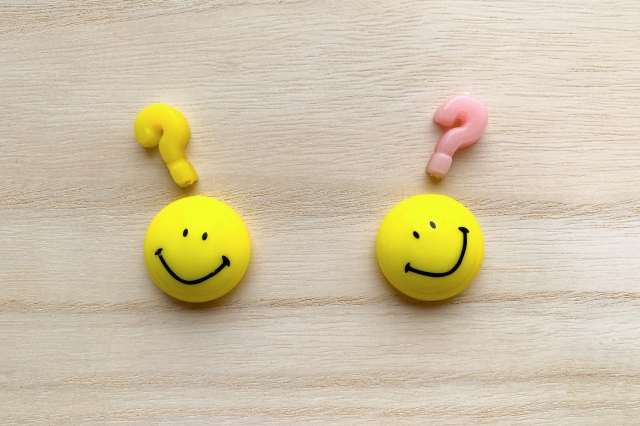
それでは、ここで、ちょっと考えてみましょう。
情報格差が起こる原因って、なんでしょう?
むずかしいことかもしれませんが、僕は抽象的なことを考えるのが得意なので、その観点から参考程度にお伝えします。
それは、急速に発達するテクノロジーに対して、インフラが整わず、従来のやり方に固執するなどして情報格差が起こっている、と考えられます(違う……かな?)。
まあ、要するに時代が原因と言えますね、うん。
シンプルにお伝えすると、時代が原因です(どん!)。
高齢者の情報格差への4つの対策

続いて、高齢者の情報格差に的を絞って、4つの対策をお伝えします。
- アナログを徹底的に強化する
- 最低限のテクノロジーに慣れておく
- 自分の得意分野に紐づけて、習得。
- 身近な得意な人に教えてもらう
順番に、解説していきますね。
その1:アナログを徹底的に強化する
高齢者の情報対策その1は、アナログを徹底的に強化する、ということです。
どういうことか。
例えば、以下の3つが、考えられます。
- 地図を確保する
- 車の運転能力を万全にする
- 本屋などの開拓できる情報源の確保
地図を確保できれば、リアルの情報源を、俯瞰できます。戦国時代の武将みたいな感じですね(かっこよく言うと)。ちなみに、最近の僕は地図の魅力に気づきつつあります(どうでもいい)。
そして、車をきっちり運転できることによって、人に会いに行けますし、土地から情報を得ることができます。
最後に、本屋などの情報源です(ここは重要)。
本屋が、知識というたしかな武器を得られるので、重要な場所になる、と思います。
あとは、雑誌や新聞の定期購読とか、テレビから専門家の意見を訊くとかになるかと思います(極めようと思ったら、もっと極められるかもしれないけど)。
他にも方法はあると思いますので、試しに1個の方法でもいいので、考えてみてはいかがでしょうか。
その2:最低限のテクノロジーに慣れておく
高齢者の情報対策その2は、最低限のテクノロジーに慣れておく、ということです。
やはり、検索だけでもできると、便利かな、と思います。
最低限の検索能力とサポート機能を使いこなせるようにしておくとよい、と思います。
スマホを使っているなら、グーグルのボタンとかを押して、気になる単語を入力し、検索ボタンを押す。そして、なるべく上位にある記事を読む。
こうするだけでも、それなりに安全に記事を見られるかと思います(参考程度にお願いします。大まかな流れ、ということです)。
あとは、相談できる場所とテクノロジーの使い方を誰かに訊くとか、実際にスモールステップで行ってみてもいいかもしれませんね。
無理にテクノロジーを使え、というわけではありませんが、最低限の保険があれば、安心してリアルでも生活できる、と思います。
その3:自分の得意分野に紐づけて、習得。
高齢者の情報対策その3は、自分の得意分野に紐づけて、習得する、ということです。
例えば、アウトドアが好きなら、アウトドアに関連するテクノロジーを誰かに教えてもらうなどして、開拓してもいいかもしれません。
その方が、苦痛なくテクノロジーに慣れる、と思います。
他にも、自分のやりたいことがあれば、それに付随するテクノロジーをちょっと活用してみてもいいかもしれません。
例えば、「野菜を販売したい」となって、他の人たちの「メルカリがいいよ!」と声を聞く。そうなってくると、「メルカリって、どんななのかな?」となって、検索し、テクノロジーに慣れ、恩恵を受けられるかな、と思います。
情報格差をなくすなら、できるだけ苦痛なく、なくせた方がいいかもしれませんね。
その4:身近な得意な人に教えてもらう
高齢者の情報対策その4は、身近な得意な人に教えてもらう、ということです。
正直、これで充分なところはある、と思います。
もちろん、これは人に依存している、と言えるかもしれませんが、どうせ人は皆依存しています(笑)。皆、一人では生きていけないのです。
そうであるならば、誰かに頼った方が普通、とも言えるかもしれません(もちろん、自力でできるところは、自力でした方がいい、と思いますが)。
テクノロジーが発達・発展している世の中。
テクノロジーが得意な人は、必ず近くにいるはずです。
家族・友人・携帯ショップ、もしかしたら役場・知り合いの知り合いなど、しっかり活用してみてはいかがでしょうか。
それでは、今回の記事をまとめます。
おわりに~格差のない社会に向けて~
今回の記事は、以下のようなことについて、紹介してきました。
情報格差の3つの例
- 高齢者のテクノロジーの不慣れ
- 情報を獲得するツールを使えない
- 教育の差異
情報格差の原因
→急速に発達するテクノロジーに対して、インフラが整わず、従来のやり方に固執するなどして情報格差が起こっている?
高齢者の情報対策
- アナログを強化
- 最低限のテクノロジーに慣れる
- 苦痛のない範囲で、慣れる。
- 身近な人を頼る
情報格差は、大きな問題として、取り扱われています。
今回、それが僕の近辺で起こりましたので、問題について考えてみました。
僕が言ったことは、参考程度のもの、と思っています。
しかし、他の記事より、気軽に、やや有益な情報もあったのではないかな、と思います。
これを読んだ人たちが、情報を参考にして、少しでも生きづらさをなくせたのであれば、ライターとして、とてもうれしく思います。
★僕(かめれもん)のnoteでは、僕がいいと思う様々な情報を掲載しています↓
スピランドより、ゆるい情報&見え方になっていると思いますので、よければご覧ください。
それでは、僕はこの辺で。
このブログでは、生きづらさから楽になる人生論と元気をチャージする遊びの情報を、ロジカル・ポップにお伝えしていけたらと思います。
よかったら、他の記事も、見ていただけると幸いです。
ここまで記事をお読みいただき、ありがとうございました。
また機会があれば、お会いしましょう。







コメント